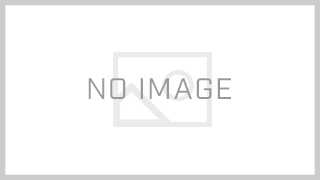1.食物連鎖
・生物どうしの食べる・食べられるという関係
・食べられる生物の方が数が多い
※植物>草食動物>肉食動物
①生産者
・植物
・光合成により有機物をつくり出す
・食物連鎖の最初に位置する
②消費者
・ほかの生物を食べて養分を取り入れる生物
ⅰ.草食動物
・植物を食べる
ⅱ.肉食動物
・草食動物を食べる
※大型肉食動物は小型肉食動物を食べる
※生物の数量的なつり合いの変化(下図)
・1. つり合いのとれた状態
・2. 何らかの理由で草食動物が増える
・3. 草食動物が食べる植物が減る。草食動物を食べる肉食動物が増える
・4. 植物が減ったので草食動物が減る
・1.にもどる:草食動物が減ったので肉食動物が減る
※一時的な増減があっても、長期的には一定に保たれる
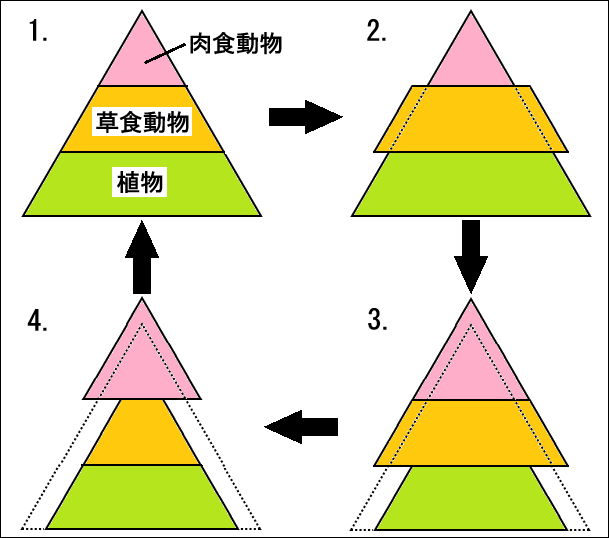
③分解者
・有機物を無機物に分解する生物
※動物の死がいや排出物、かれた植物などを食べる
ⅰ.菌類
・カビやキノコのなかま
・胞子で増える
ⅱ.細菌類
・乳酸菌、大腸菌など
・分裂して増える
※消費者の一部にも分解者がいる(ミミズ、ダンゴムシなど)
2.物質の循環
・生産者(植物)、消費者(動物)、分解者(菌類・細菌類)の活動により、炭素や酸素が自然界を循環すること
・炭素は食物連鎖や呼吸などにより、有機物や二酸化炭素として自然界を循環する
3.酸素と二酸化炭素
①二酸化炭素
・生産者・消費者・分解者ともに、呼吸をして二酸化炭素を出す
②酸素
生産者は光合成をして酸素を出す
漢字の読み方(タップで開きます)
1.食物連鎖
・食物連鎖:しょくもつれんさ
・菌類:きんるい
・細菌類:さいきんるい
ざっくり理科3年にもどる