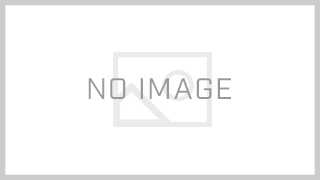太陽系、月と金星の見え方(ざっくり)
1.宇宙の広がり
①恒星
・みずから光を出してかがやいている星
例:太陽、星座を構成する星
②銀河
・恒星が多数(数億~数千億個)集まっている天体
例:銀河系、アンドロメダ銀河
2.太陽系の天体
①太陽系
・太陽とそのまわりを公転する天体の集まり
※太陽系は銀河系という銀河に属している
②太陽
・地球からもっとも近い恒星
・表面温度は約6000℃
・黒点…太陽の表面にある黒い部分。まわりより温度が低い
③惑星
・恒星のまわりを公転する天体
・みずからは光を出さない
・太陽系には8つの惑星がある
・太陽から近い順に、水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星
④衛星
・惑星のまわりを公転する天体
例:地球の月
⑤小天体
・小惑星:火星と木星の間に多い
・すい星:氷の粒やちりが集まった天体。長いだ円軌道をえがく
3.月の見え方
①月の動き
・月は東の空からのぼり、南の空を通って西の空にしずむ
※地球の自転による見かけ上の動き
②月の満ち欠け
・月は太陽の光を反射して光って見える
・地球からの見え方が日によって変わる
※月は地球のまわりを公転しているため
・新月→三日月→上弦の月→満月→下弦の月→次の新月と、約29.5日の周期で見え方が変わる
※満月より前は右側が光って見え、満月の後は左側が光って見える
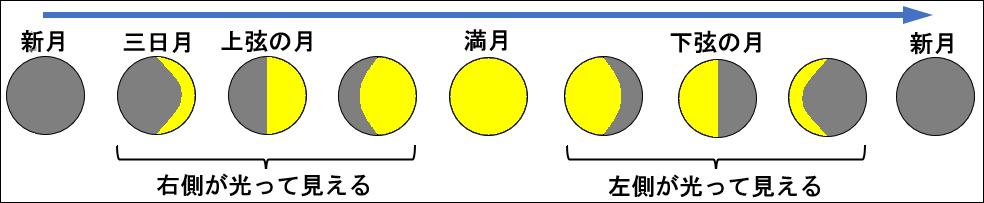
4.日食と月食
①日食
・月によって太陽がかくされること
→日中の時間帯に起こり、太陽がさえぎられうす暗くなる
・太陽・月・地球の順に一直線に並んだときに起こる
※日食のときは必ず新月
②月食
・月が地球のかげにはいること
・太陽・地球・月の順に一直線に並んだときに起こる
※月食の時は必ず満月
5.金星の見え方
①金星の満ち欠け
・月と同じく、金星も太陽の光を反射して光って見える
・地球との距離によって見える大きさも変わる
・地球より内側を公転しているため、真夜中に見ることができない
②金星の見え方
ⅰ.地球から近いとき
・大きく見える
・欠け方は大きい(三日月のような形)
ⅱ.地球から遠いとき
・小さく見える
・欠け方は小さい(満月に近い形)
③金星が見える時間
ⅰ.よいの明星
・日の入り後に、西の空に見える金星
ⅱ.明けの明星
・日の出前に、東の空に見える金星
※天球上で太陽に近いところに見える
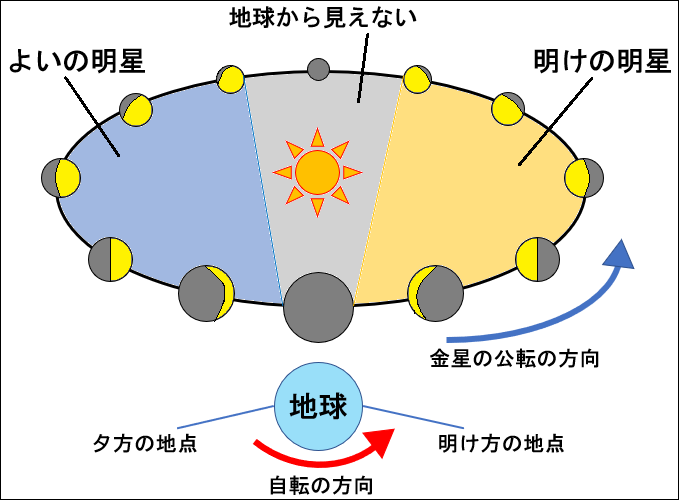
漢字の読み方(タップで開きます)
1.宇宙の広がり
・恒星:こうせい
・銀河系:ぎんがけい
2.太陽系の天体
・黒点:こくてん
・惑星:わくせい
・天王星:てんのうせい
・衛星:えいせい
・小天体:しょうてんたい
・小惑星:しょうわくせい
・すい星:すいせい
3.月の見え方
・上弦の月:じょうげんのつき
・下弦の月:かげんのつき
4.日食と月食
・日食:にっしょく
・月食:げっしょく
5.金星の見え方
・明星:みょうじょう
ざっくり理科3年にもどる